創作奇譚4 “長い坂道の先に立つ病院”
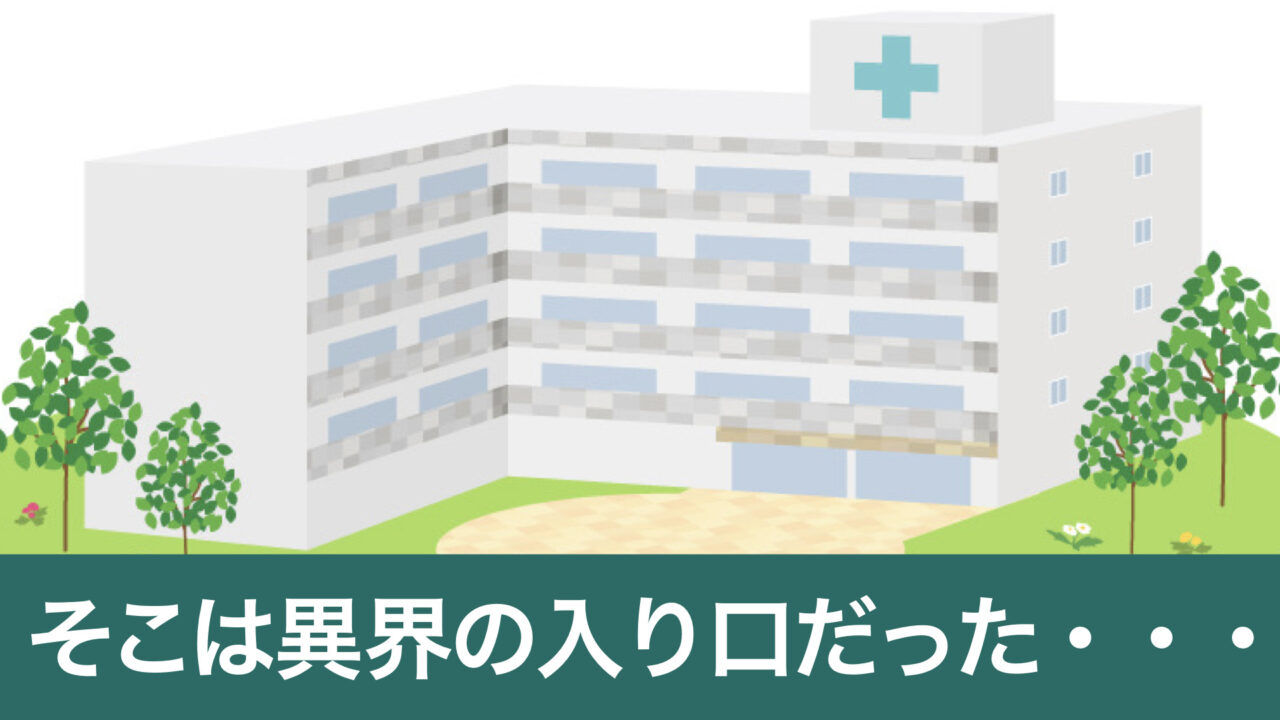
はじめに
本投稿では、創作物語 第七作 ”長い坂道の先に立つ病院” を発表します。
風景画を描くかの如く心の内を写生してみたいと思い、本作を書き始めました。そして、キュビズムの如く、部分的に切り取った現実と空想を多面的につなぎ合わせようと試みました。そうして出来上がった掌編小説が本作です。
うつ病で入院した妻を見舞うため、私は病院に向かったのですが、それが異界への入り口だったとは・・・
なお、誤解がないようにあえて事前に申し上げておきたいことがあります。本作品はフィクションです。登場する人物名・駅名・病院名は全て架空の設定です。
《創作ショートショートのテーマ》
辛い毎日から逃れるために、思考と感情のバランス調整の一環として掌編小説(ショートショート)の創作を始めました。ペンネームは香月融です。
「発達障害児の世界」と「健常の大人の世界」とが不連続に交錯融合する「奇妙で切ない不条理の世界」が主題です。具体的には、発達障害者・精神障害者・生きづらさを感じている人々・世の中の偏見や差別に苦しんでいる人々が登場する物語です。
およそ2,000文字から10,000文字の範囲で創作していますので、5−10分くらいで読めます。
本編:長い坂道の先に立つ病院
突然、妻から「鬱が酷くなってきたから1ヶ月ほど入院したい」と告げられた。
確かにこの3週間くらいは昼夜を問わず、妻はほとんど寝たきりだった。もちろん、私は妻の希望を承諾して、返答した。
「辛いよね。何もしてあげれなくて、申し訳ないよ。病院でしっかり養生した方がいいよね。それじゃ、早い方がいいと思うけど、いつから入院する?」
妻からは意外な答えが返ってきた。
「入院日はもう決まってるよ。来週の月曜日。入院の手続きや準備も終わってるの。全部一人でやっちゃった。」
入院当日、妻は私が病院まで付き添うことを頑なに拒んだ。そして、勝手にタクシーを呼んで一人で出て行った。自宅前で私と別れるとき、妻は無表情ながらどことなく嬉しそうに見えた。
その病院は山の中腹にあって、自宅から車で2時間もかかった。妻は1年前から適応障害にともなう鬱病を患い、毎月1回の頻度で通院していた。
「そもそも、なぜそんな遠方の病院を選んだのか?」と妻に訊いても、彼女は「なんでも!」と繰り返すだけだった。
妻が入院した後、私は仕事・家事・子供の世話とてんやわんやの毎日が続いていた。そんな生活も2週間ほど過ぎて少し慣れてきた頃、取引先の担当社員と一緒に昼食をとっていた。突然、不意打ちのごとく、私の携帯電話に妻から「今日中にキャラメルとチョコレートを買ってきて欲しい」とメールがあった。
面会時間は18時までとのことだったので、私はやむなく15時に商談を切り上げてその足で病院に向かった。京都駅地下街のお土産屋でギフト用のチョコを、その数軒隣りの高級スーパーでキャラメルを買い、急いで電車に乗り込んだ。
ローカル線を乗り継ぎ1時間半ほどかかって、最寄の熊頭駅1に着いた。小さな無人駅ながら、周辺はきれいに整備され、植林の緑がきれいだった。

すでに17時を過ぎて日差しは和らいでいたが、改札を出るとうっすらと額に汗が滲んだ。携帯電話に目をやると、「この夏一番の猛暑を記録」とのニュース記事がディスプレーに表示されていた。
駅前に並ぶ3軒ほどの飲食店を通り過ぎると、病院の方向を示す標識が見えた。そこからは一本道だった。携帯のGPSで位置確認すると、病院まで1km ほどの距離だ。
チョコが溶けないかと心配しながら、私は緩やかな坂道を急ぎ足で進んだ。坂の勾配はだんだんとキツくなり、道は50メートル置きに左右にくねっていた。
病院はなかなか現れなかった。背中が汗びしょびしょになりながらも、黙々と坂を登った。どういうわけか、足が思うように運ばない。走ろうと試みるが、なぜだか走れない。
得体の知れない重荷を引きずっているかのようだ。面会の締め切り時間まで残り40分に迫っていた。私はかなり焦った。
それでもへこたれずにひたすら坂を登り続けると、どこからともなく焦げくさい匂いがしてきた。煙は見当たらない。20メートル前方、道はUターンするかのように急激に湾曲した。
突如、灰色の野良猫が物凄いスピードで道を横切り、山の中へ消えていった。その方角に向かってふと顔を上げると、脇の樹樹の背後に巨大なコンクリートの建造物が見えた。

坂を上り切ると、広い駐車場と病院の全容が現れた。病院はきれいな4階建てで、新館のように見えた。玄関の右には「熊頭市立 こころのホスピタル2」と縦書きされた小振りの表札がかけられていた。
私は小走りに受付に向かい、妻への面会予約の旨を告げた。応対した職員は申し訳なさそうに言った
「本日は本館から入院病棟への通路が工事中で使えませんので、野外の裏口をご案内します。」
しばらく待っていると、別の職員が現れ、入院病棟まで連れて行ってくれた。
妻が入院している病棟は2階建てで、本館の背後に隠れるかのようにひっそりと在った。本館とは対照的にいかにも昭和風の古びたモルタル建築だが、施錠管理された重厚な裏口扉だけは新調されたばかりに見えた。
その入り口からしばらく歩くと受付らしきカウンターが見えた。そこで、持ち物と妻への贈り物をチェックされた後、さらに奥に進むと二重のオートロック扉となっていた。ここから先が重症患者専用の隔離病棟だ。
そこでもインターホンを通じて受付があった。中に入ると、担当の看護師が待ち構えていた。私の視界一面にラウンジのような広いスペースが広がり、大きなテーブルが3つ置かれていた。
その一角で、妻は年輩の女性と話し込んでいた。声は聞こえない。女性は話している間、ずっと両手で何か裁縫でもしているかのような仕草を繰り返していた。
私は妻に声をかけようとしたが、本能的に躊躇して立ち止まった。私の内心を悟ったかのように看護師は「こちらへ」とさりげなく私を面会室に誘導した。面会室の扉を開くと、小さなテーブルを挟んで2つづつ椅子が用意されていた。
しばらくすると、妻が別の看護師に連れられてやってきた。笑顔はない。少し痩せたようだが、彼女のすっぴん顔の肌は妙にすべすべしていた。異様に若返っているかのように見えた。
買ってきた品を妻に手渡すと、彼女はそのギフト包装を見て怪訝な表情を浮かべた。「高級チョコなんだけど、プレゼントだから・・・」と私が説明を始めようとするや否や、彼女は無言のまま包装の紙を無造作に破り缶の蓋を開けた。中に入っているものがチョコレートであることを確認するとすぐに蓋を閉じた。
一方、キャラメルについては、箱に印刷された銘柄、原材料、内容量、賞味期限、栄養成分値を小声で読み上げながら確認した。それで納得したのか、開封はしなかった。
病棟の中央には30m四方ほどの吹き抜けの中庭があった。鉄格子が付いた窓から中庭を見下ろすと、妙に傾いたオリーブの木が立っていた。
木のそばには2つのベンチがあり、その一つに小柄な女の子が座っていた。見た目は中学生くらいだろうか? 真夏だというのに、その子は厚めの長袖シャツを着て、首にはチェック模様のマフラーのようなものを巻いていた。

私の視線に気が付いた妻はこういった。
「あの子、かわいそうなの。いじめを苦にして自殺未遂したらしいのよ。毎日、誰とも喋らないであそこに座ってるわ。」
私は絶句した。直感的に私は話題を変えなければと思い、我が子の話を振った。
「子供たちも元気でなんとかやっているよ。大介は時々癇癪を起こすけど、ADHDの薬はちゃんと飲んでくれているから大丈夫。綾は不登校のままで部屋に閉じこもっているけど、自傷行為はしていないよ。」
妻は無反応だった。その後、妻とはポツリポツリと会話を交わしたと思うが、話の中身は憶えていない。10分ほど過ぎただろうか、面会室にやってきた看護師が「面会時間終了」と私たちに告げた。
妻は無言のままその看護師に連れられて自室に帰って行った。私は受付で持ち物の返却と職員への挨拶を適当に済ませて、扉をかいくぐるかのようにして隔離病棟を出た。
なんとなく来た道とは違うような気がしつつも成り行きに廊下を進むと、曲がり角付近の壁に掛かった絵が目に入った。患者が描いた絵のようだ。よく見ると絵の右端に、「かみかわ とおる 11さい」と縦書きされたテープが貼ってあった。
八つ切りの画用紙には「海中を泳ぐ鯨の親子」が水彩絵の具で描かれていた。子供の鯨は妙に白かった。2匹の鯨にはともに明確な輪郭線がなく、肉の塊がおぼろげに海中で揺らいでいるかのようであった。
私はどういうわけか「鯨たちは徐々に海水と融合してやがて跡形もなく消滅する」と確信した。かなり長い時間、見惚れていたように思う。
廊下を突き進むと外来診療の待合室に出くわした。18時はとうに過ぎているだろうに、まだ数人の患者が診察を待っているようだった。不思議なことに、彼らはマネキンのごとく、ピクリとも動かなかった。
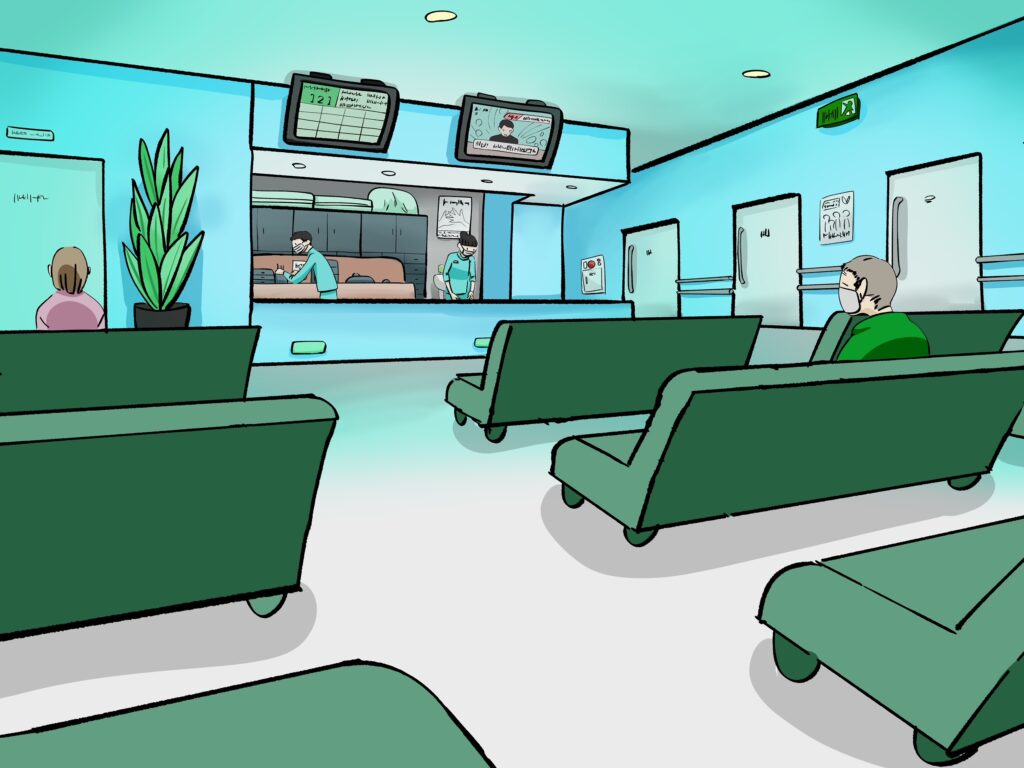
どうやら、私は入院病棟を出た後、誤って外来診療の病棟に迷い込んでしまったようだ。待合室を横切ると長い廊下があった。その先に出入り口が見えた。私は逃げるようにして病院を出た。
眼下に熊頭駅が見えた。駅舎の背後に広がる海に沈みゆく、四角い茜陽3に私は恍惚とした。
終わり
【脚注】
1:熊頭駅・・・架空の駅名(本作に登場する病院の最寄駅で、「くまずえき」と読む)
2:熊頭市立 こころのホスピタル・・・架空の病院名(本作に登場する精神病院で、冒頭の4文字は「くまずしりつ」または「くまずいちりつ」と読む)
3:茜陽・・・夕焼け(西陽が輝く赤色の空を表現した造語で、「あかねび」と読む)
編集後記(私の体験)
この物語は完全なフィクションですが、アイデアのヒントとなった出来事は多数あります。その中でも、決して忘れることができない思い出をお話しします。
【私の体験】
重篤な精神不安定で隔離病棟に入院していた息子を見舞ったとき、廊下ですれ違いざまに中学生くらいの少女が小走に看護師に近づいていく光景が目に入りました。
その子は割と大きな声で「自殺防止プログラムが終わったから、外出許可出してよ〜」とはにかみながら看護師に懇願しました。
私は頭をかち割られたような衝撃を受けました。
まだ12−13歳ほどの無垢な少女が自殺するほどに悩み苦しんでいたのかと思うと、病院から帰りの車の中で涙が止まりませんでした。
この時の少女の服装、顔、声、看護師の困ったような表情、周りの風景はカラー映像のごとく鮮明に私の脳裏に焼き付いています。
そして、私自身が苦難のどん底に落ちた時、この光景が自然と浮かんできます。今となっては、逆に私の方がこの少女から勇気をもらったと感じています。
参考情報
●【まとめ記事】その他のショートショート(掌編小説)
2023年3月2日
香月 融
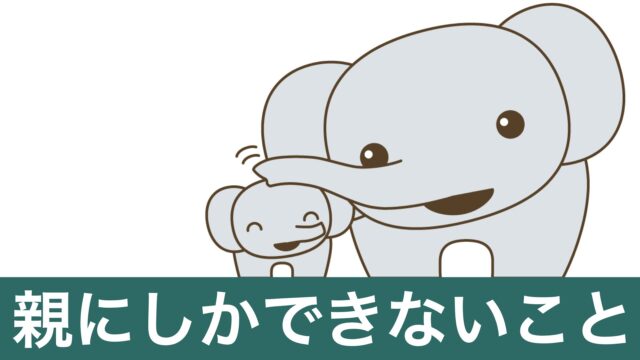


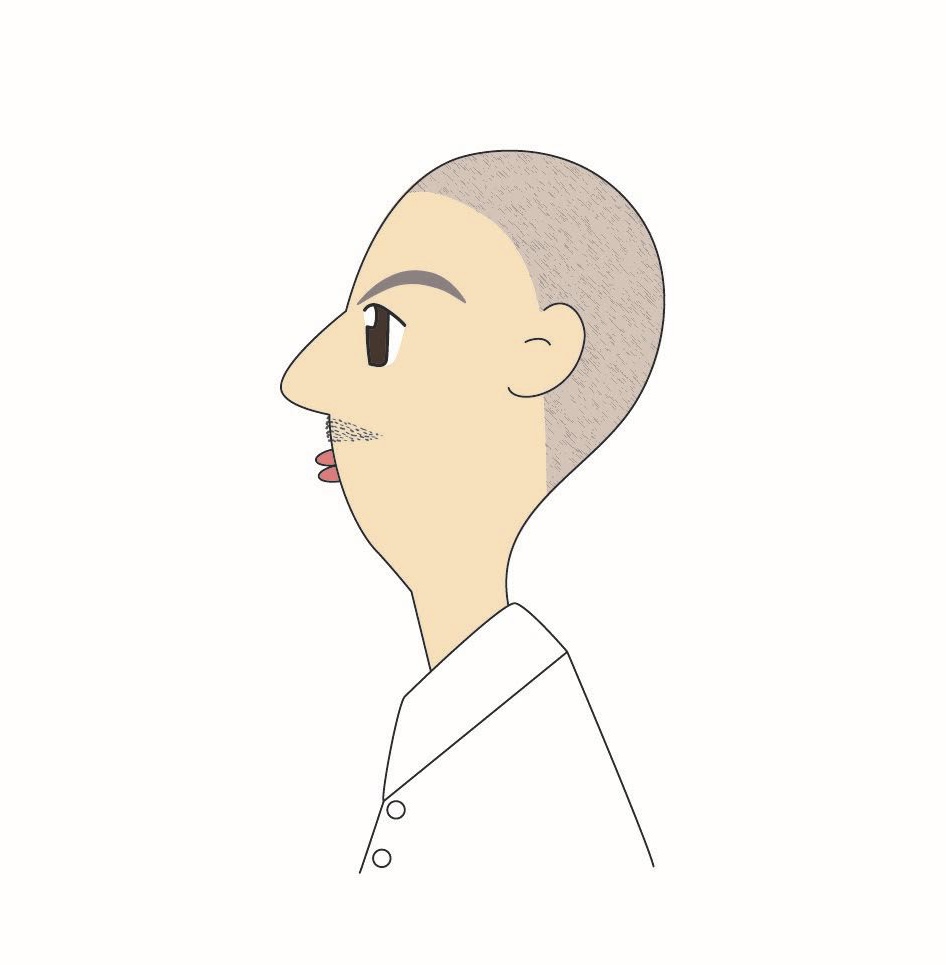
 プロフィールの詳細は
プロフィールの詳細は 発達障害を克服して偉業を成した著名人リストをトップページのピックアップコンテンツ
発達障害を克服して偉業を成した著名人リストをトップページのピックアップコンテンツ